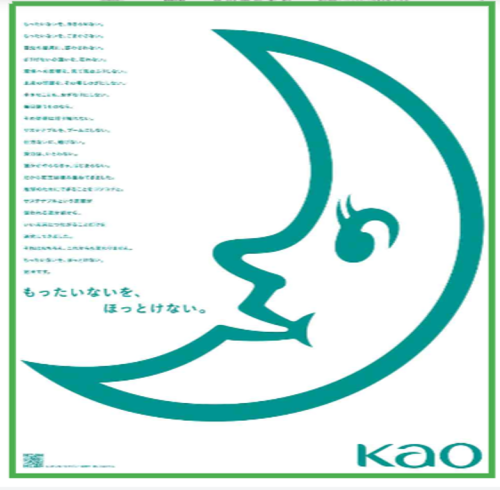体験消費時代のマーケティングヒント

みなさんこんにちは、和田康彦です。
みなさんは「チャコット」というブランドをご存じですか。
チャコットは、バレエを習う子どものレッスンウエアから世界で活躍する一流アーティストの衣装まで、バレエやダンスに関わる多彩な商品、サービスを展開するブランドです。
同社は、オンワードグループに属する創業70年の老舗企業。スタジオの運営、公演・コンクールの協賛など幅広い活動を行い、芸術を愛する人々と伴走しながら、広く芸術文化を支え続けてきました。
しかしながら、演劇、芸術領域は、コロナの影響を大きく受け厳しい状況が続いています。また人口減少に伴い、そもそも日本国内のバレエ人口自体も減少が続いています。昭和音楽大学バレエ研究所「日本のバレエ教育に関する全国調査」によると、国内のバレエ人口は、2011年の40万人から2021年では25.6万人に減少しています。
▪芸術とは、人生を芯から美しくするものである。
コロナ禍に先立つ2018年に着任した馬場社長は、バレエを中心とした魅力とは何かを考えていったとき、これまで芸術文化を支え続けてきた専門性は維持しながら、「芸術とは、人生を芯から美しくするものである」と新たに捉え直すに至ったといいます。そして、このコンセプトを軸に置きながら、広く心身の美のために何ができるかを追求していきます。
バレエは敷居が高いというイメージもあるため、経営戦略として“特定の顧客”だけでなく、“多くの生活者”を対象とする「クローズからオープンへ」を掲げ、新たな戦略を次々と打ち出しました。そして戦略の核になるブランドフィロソフィーを、“人生を、芯から美しく。”と設定しました。
▪フィロソフィーを核にしたブランド展開を強化。
祖業であるバレエで培ってきた技術を使って、バレエを知らない人にも広くチャコットを知ってもらいたい。結果として、バレエ自体にも興味を持っていただけるような、そんな循環をつくっていきたい。というのが馬場社長の熱い思いです。
そこで“人生を、芯から美しく。”を拡げていくため、現在、バレエ製品以外のウェルネスブランドとして2つのブランドの展開の強化を進めています。
バレエ関連に次ぐ売上を稼いでいるのが、ステージメイク用品として1997年から販売を開始し、原材料や日本製にこだわった開発・製造を行うことで高い信頼を得ているコスメ製品です。ステージライトのもとで映える発色、汗・皮脂への強さなどはプロのアーティストからも絶賛されてきました。
2021年4月には、ふだん使いにも対応できるアイテムとして大幅なリニューアルを敢行。新たに「チャコット・コスメティクス」として、全国26の直営店の他、バラエティショップ、コスメ専門店等での販売を強化。購入者の約6割をバレエに関わっていない一般消費者が占めているといいます。
また、2019年に始動した「チャコット・バランス」というフィットネスウエアブランドは、ヨガやピラティスに適しているものの、あえてシーンを限定しない、心身を「整える」ためのバランスウエアという位置づけでスタート。
バレリーナが身に着けるウエアの技術が凝縮されているため、可動域が広く動きやすいのが最大の特徴です。レギンスやトップスの主力素材にはレオタード素材を多用しているため、やわらかく肌になじみます。スポーツメーカーのフィットネスウエアが『鍛える』ためのアクティブなアイテムであるのに対して、同社のアイテムは、バレエウエアの専門技術を生かし、所作の一つひとつが美しく見えるエレガントさを追求しているところが強みです。
さらに、2020年10月に新商品として投入したデニムは、「バレエスキニー」と命名してSNSで発信したころ、想像を超える大きな反響があり、姿勢を「整える」デニムとして人気商品となりました。フィットネスウエアはコロナ禍でも売上が好調に推移しており、現在では単独のショップも誕生するまでに成長しています。
▪クローズからオープンへ。
一方で、「クローズからオープンへ」を加速するため、2022年3月、代官山にチャコット本店をオープン。代官山本店は、ブランドフィロソフィーとして掲げている“人生を、芯から美しく。”を具現化する次世代型グローバル・フラッグシップストアと位置づけています。
地下1階、地上5階建て、建物全体がアート作品ともいえる館内には、美しいバレエ衣装が飾られ、各階にアート作品を配置しています。4階のレストランは天井を高めにとり、スタジオはまるで緑の公園の中で踊っているかのような気持ちになるといいます。
この代官山本店は、“人生を、芯から美しく。”することを実際に体感できる場所としての位置づけです。商品を売ることだけが目的ではなく、代官山の丘で過ごす時間を楽しんでいただき、食やスタジオなどをきっかけにお客様自身のライフバランスに目を向けてもらいたい、バレエ文化にも親しんでもらいたい、という想いが詰まった、いわばチャコットのふぃろを発信する場所といえます。
自社ブランドのパーパス(存在価値)は何か、を改めて深く探求し、そこから導き出されたフィロソフィー“人生を、芯から美しく。”を核に、新たな戦略を次々に打ち出していく。
戦略の核になるのは、ぶれないフィロソフィーであることを学べる事例です。

みなさんこんにちは、和田康彦です。
消費のパターンとは、①不安、不満などを解決するソリューション型消費 ②もっと生活をよくしたいという向上心を充たす前向き消費に2分されます。
別の言い方をすると、「困ったを減らす」消費と「うれしいを増やす」消費ですね。
このところ物価高や給料が上がらないなどのニュースが連日のように流れてきますが、そんな不況の中でも女性の向上心は旺盛です。
男性はどちらかというと、仕事や会社、趣味に価値観を置いていますが、女性は自分自身や家庭、友達を大切に生きています。つまり、女性は男性に比べて、自分や家庭(暮らし、生活)つながりの中で向上させようとする意識が強いといえます。
このような向上心が強く、自分を高めていきたいと考える女性が今の消費をリードしているのです。
今よりも美しくなりたいと考える人がサプリメントを購入し、今よりもスキルを上げたいと考える人が通信講座を受講する。今よりも自分の住まいを素敵にしたいと考える女性がインテリアを購入したり、リフォームを計画しているのです
先日も、今年の4月に銀座にオープンした「DAISO」、300円ショップの「Standard Products by DAISO」、「THREEPPY(スリーピー)」という3つのスタイルが集積したダイソー基幹店を訪れましたが、3業態とも、商品のデザイン力を高めて、若い女性やカップル客で賑わっていました。
また、300円ショップの3coinsや業務スーパーの業績も絶好調です。値上げラッシュの中でも、感性価値とコスパの高いブランドにますます支持が集まっています。
これからの時代は、女性の向上心に応えることこそが消費につながります。
あなたの会社でも、不況の中でもなんとか工夫して楽しみたい、良くしていきたいと考える女性に、「うれしい」を提供できる価値をどんどん提案していきましょう。

みなさんこんにちは、和田康彦です。
1970年2月に日本最初のハンバーガーチェーンとして誕生した「ドムドムハンバーガー」。最盛期には400店舗展開していたものの、その後マクドナルドやモスバーガーといった競合企業に客を奪われ、現在は29店舗まで縮小。倒産の危機に直面してきました。
しかし、独自に開発した「丸ごと!!カニバーガー」や「丸ごと!!カマンベールバーガー」など「丸ごと!!シリーズ」がSNSなどで注目を集め、2021年3月期に続き2022年3月期も2期連続で黒字化を果たしました。
▪ハンバーガー業界は2極化
ハンバーガー業界は、マクドナルド、ロッテリアなどの低価格チェーンとシェイクシャック、ウマミバーガーなどの高価格チェーンの2極化が進んでいます。
ドムドムハンバーガーは、低価格帯チェーンのひとつですが、低価格市場は、マクドナルド、モスバーガー、ケンタッキーフライドチキンの大手3社が市場の8割を占めています。
▪おいしさはお客様との最低限のお約束。その上をいくものをつくる。
ドムドムハンバーガー復活の立役者藤崎忍さんは、入社から9年で社長に抜擢された異色の人物です。夫の急死後、39歳で初めて働き、SHIBUYA109のブティックの店長、居酒屋オーナーを経て2018年にドムドムフードサービスの社長に就任しました。
社長就任後にまず藤崎さんが取り組んだことは、「おいしいものをつくること」と「クレームをなくすこと」。
「おいしさはお客様との最低限のお約束。その上をいくものをつくる。」を信条に、原価率や人件費比率、QSCといった当たり前のことをやりつつ、独自性のある商品を模索してきました。
▪「丸ごと!!シリーズ」が話題に。
独自性を模索するため、ほぼ毎月ひとつは新商品を発売することに注力。そこから生まれたのが、素材を丸ごと挟んだ「丸ごと!!シリーズ」です。
その中のひとつ、2020年9月に復活販売し、2021年1月から期間限定で再販している「丸ごと!!カニバーガー」(単品990円)は、殻の柔らかい大きめのソフトシェルクラブを丸ごと挟み込んだカニバーガーです。
▪あえて非効率な道を選ぶ。
通常は店舗に殻のついた状態の材料が届き、それをただ揚げるだけですが、カニバーガーはおいしさを追求するために、あえてリスクがあり非効率なオペレーションを敢行しました。
店舗に冷凍のカニを送り、流氷解凍するところからスタート。手足がもげないように優しく衣をつけて揚げていきます。
このような手間をかけた調理法が、単品価格990円(税込)という価格を超えた上質な価値を実現。インスタ映えする見た目のインパクトの強さと相まって、SNS上で話題になり、ドムドムハンバーガー復活の牽引役になりました。
▪独自性追求の挑戦は続く。
2022年7月現在も、「ゴーヤチャンプルーバーガー」や「はみ出る!アジフライバーガー」など、独自性追求の挑戦は続いています。
今は、どこに行ってもおいしいものが食べられる時代。お客様もおいしいものには慣れています。だからこそ、さらにその上をいく必要があります。そして、見た目がインスタ映えするインパクトの強さも同時に求められています。
その店やブランドでしか提供できない独自の価値に磨きをかけることが、企業が成長していくための原理原則です。
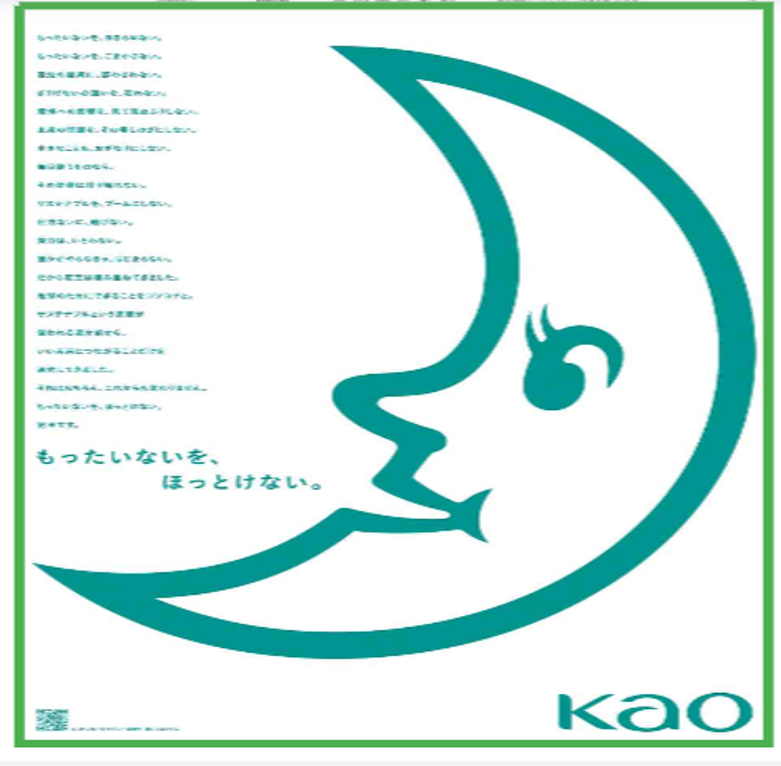
2022年7月19日付日本経済新聞に、大手消費財メーカーの花王が「もったいないを、ほっとけない。」というキャッチフレーズでステキな全面広告を掲載していましたのでご紹介します。
もったいないを、ほっとけない。
もったいないを、あきらめない。
もったいないを、ごまかさない。
目先の結果に、惑わされない。
さりげない心遣いを、忘れない。
環境への影響を、見て見ぬふりしない。
未来の問題を、その場しのぎにしない。
小さなことも、おざなりにしない。
毎日使うものなら、
その効果は計り知れない。
サスティナブルを、ブームにしない。
仕方ないに、逃げない。
努力は、いとわない。
誰かがやらなきゃ、はじまらない。
だから花王は、積み重ねてきました。
地球のためにできることを、コツコツと。
サスティナブルという言葉が
使われる遥か前から。
いい未来につながることだけを
追求してきました。
それはもちろん、これからも変わりません。
もったいないを、ほっとけない。
花王です。
いかがでしたか。
私たち一人ひとりのこれからの時代の生き方のヒントにもなる、とてもいい広告だと思いました。
目先の結果に惑わされず、さりげない心遣いを忘れず、環境への影響も見て見ぬふりをしない。
小さなこともおざなりにせず、地球のためにできることをコツコツ積み重ねる。
人も企業も、いい未来につながることだけを追求していけば、きっとこれからの時代も成長していけるのではないでしょうか。

みなさまこんにちは。和田康彦です。
東京の松屋銀座では、化粧品の2022年 5 月の売上が前年比 150%とようやく需要が戻りつつあります。
行動制限の解除によって、人と会う機会が増え、「少しおしゃれをして出かけよう」、「久々に会う人との会食でマスクを外すから口紅をきちんと塗ろう」という女性が増え、メイクアップする気持ちが高まっているようです。
とはいえ、「長い間使っていなかった化粧品の劣化がが気になる。トレンドカラーが変わって、今持っているものでは気分が上がらない。とはいえ、捨てるのはもったいないし・・・・・」と思っている女性も多くいるのではないでしょうか。
そこで松屋銀座では、2022年6月30日まで、メイクアイテムの買い替え需要を促すキャンペーンを実施しています。
コロナ禍のマスク生活で暫く使っておらず、今の気分ではないカラーや劣化が気になる化粧品を回収し、
回収した化粧品は、「COSME no IPPO」による、カラーコスメをクレヨンへアップサイクルするプロジェクトに活用するというものです。
▪「捨てると損をするようでもったいない」という女性心理
多く女性は、クローゼットの中の洋服がいっぱいでも、捨てると何か損をするような気がして、着なくなった服でもなかなか捨てられないものです。
化粧品に関しても同じような気持ちを持っている女性はたくさんいると思います。「まだ、少し残っているので捨てるのはもったいない。まだ使えそうなので手元に置いておこう・・・・」
そんな、「損失を回避したい」という気持ちが、女性の買いたいと思う気持ちにブレーキをかけているのです。
例えば、同じ1万円でも、1万円をもらった喜びより、1万円を失った苦痛や不満足の方を、人間は大きく感じてしまいます。
そこで人間は、損失を回避しようと考えて行動するようになるのです。行動経済学では、このような行動を「損失回避性」と呼んでいます。
特に買い物においては、女性は「買い物で失敗したくない」という心理が大きく働いています。ですから、少し遠くても1円でも安いスーパーヘ足を伸ばしてしまうのですね。
松屋銀座の今回のキャンペーンは、「化粧品を買い替えたいけれど、捨てるのはもったいないし・・・」と、買い替えをためらっている女性に対し、「あなたが不要になった化粧品は、アップサイクルして社会のためにも役立ちますよ。」と、SDGsもほのめかして背中を後押しする内容になっています。
先行き不透明で不確実な時代には、女性は今持っているものを失いたくない、損をしたくないという損失回避の心理がより大きくなっています。
モノが溢れ、慌ててモノを買う必要ななくなった今こそ売ることばかり考えるのではなく、どうすれば女性客が買いたくなるのか、というマーケティングの発想が求められています。