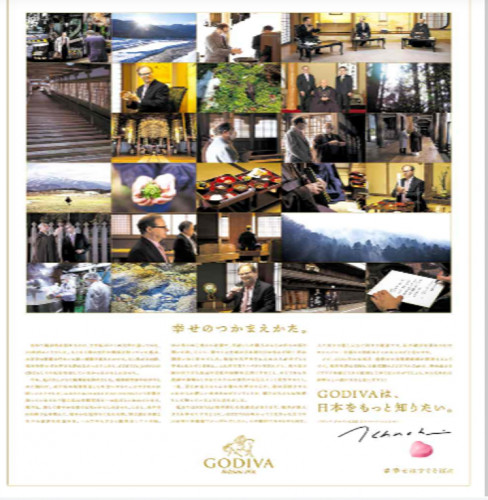体験消費時代のマーケティングヒント

みなさんこんにちは。和田康彦です。
あなたの会社では、女性リーダーの登用は進んでいますか。
女性が消費の決定権の8割以上を握っている今、女性消費者の気持ちがわかる女性社員をリーダーに登用することは、企業業績の向上に必ず寄与します。
つまり、女性の視点を生かして消費に結びつけることが今後の企業の成長につながるわけです。
これまでの男性社会は、数字の上で経済発展だけを見据えてきましたが、過去の延長線上に未来は描けません。画一的な視点では、どれだけ会議を重ねても同じ意見が出て終わってしまいます。
今こそ、多様な価値観を持つ人が意思決定の場に入っていろいろな視点から意見を出し合わなければいけません。
特に新型コロナウイルのス感染拡大によって、暮らしに対する価値観やライフスタイルがかなり変わりました。
例えば、在宅ワークをしながら、家事や子育てをしなければいけない女性が増えましたが、女性はその中でも「生活の幸せ」を求めることに貪欲です。
生活のことをいちばん知っているのは女性です。女性社員を社内で活用することで、お客様に対してももっとしなやかな見方ができるようになり、柔軟な経営ができるようになります。
ニューノーマル時代を生き残るためには、女性視点を経営に取り入れて、女性消費者に支持される会社を目指していきましょう。
●セブン&アイ、女性の執行役員を3割に
これまで勝ち組といわれていたコンビニ業界も、新型コロナウイルスの感染拡大によって業績不振に陥っています。
コンビニ業界の中でも超優良児といわれてきたセブンイレブンでも、2020年度の1日当たりの平均店舗売上高は前年比2.1%減の64万2千円に減少し、客数に至っては10%減になりました。
これまでの成功の方程式は崩れ、立地ごとの対応や女性に支持される店づくりを進めていくことが目の前の課題になっています。
コンビニ事業の女性客比率は、2003年には35%でしたが、2019年には42%に増加。まさに女性消費者の時代を象徴しています。
そこで、セブン&アイホールディングスではグループ会社の女性幹部の比率を高め、増加している女性客に支持される店づくりを進めて、新たな成長につなげていく計画です。
具体的には、2026年2月期までに、執行役員の女性比率を現在の1割から3割に高めていく予定です。
経団連では、2030年までに役員らに占める女性比率を30%にする目標を掲げていますが、セブン&アイグループは4~5年前倒しで達成することを目標にしています。
大手コンビニチェーンも、ようやく女性消費者の時代を見据えた戦略の必要性に気づいたようです。
女性客に支持される品ぞろえや店舗レイアウト、接客サービスで女性客を笑顔にできたブランドのみが勝ち残っていく時代です。

みなさんこんにちは。和田康彦です。
株式会社ドミノ・ピザ ジャパンは、5月19日(水)、全世界のドミノ・ピザ初となる「世界一透明なドミノ・ピザ」をお台場にオープンしました。
「世界一透明なドミノ・ピザ」は、冷蔵庫からキッチンまで、すべてがガラス張り。さらに、キッチンには、ピザ作りの工程を克明に捉えるライブカメラが3か所に設置されています。1台目のカメラは注文ごとに生地を1枚ずつ手作業で伸ばす様子を、2台目は高温のオーブンの中に向けられ、生地が膨らみ、チーズが溶け出し一枚一枚こんがりと焼きあがる様子を捉えます。3台目は、焼きあがったピザをすぐに手際よく正確にカットしBOXに入れる様子を映します。
これらのライブ映像は、ドミノ・ピザ公式サイトでも配信されおり、店舗に行けなくても、どこからでもピザ作りの様子が見られるというサービスです。
自宅でも、職場でも、スマホでも、PCでも、誰でも、どこでも見ることが可能です。加えて、店内の大型モニターにはピザの注文を受けている件数やデリバリーの状況がリアルタイムに表示されます。
ドミノ・ピザでは、「世界一透明なドミノ・ピザ」のオープンによって、お客様の「ピザ生地は出来あいのものを使っているだけではないか。」「ピザは冷凍されているものを解凍しているだけではないのではないか。」「ピザはレンジで適当に温めているだけではないか。」といった不安を、安心で楽しいものに変えていくことを目指しています。
インターネットというバーチャルなお店が台頭する中、リアルであるという強みを生かして何ができるかが今問われています。
リアルなお店の強みは、空間と時間を持っていること。つまり「ライブ感」をお客様に味わってもらえることです。
ライブは、視覚だけでなく、五感を使って味わえるので、ワクワクドキドキします。その醍醐味が、お客様の心をグッと惹きつけるのです。
特に、ワクワクが大好きな女性消費者はライブ感が大好きです。五感を刺激することで、思わずニッコリ笑顔にすることができます。
ドミノ・ピザの「世界一透明なドミノ・ピザ」は、まさにライブ感を前面に打ち出すことで、女性を笑顔にする店づくりを目指しているといえます。

みなさんこんにちは。和田康彦です。
コロナ禍でEコマースを利用する女性が増えています。そんな中、個人や工房など21万人のクリエイターが登録・販売するハンドメイドマーケットプレイス「クリーマ(CREEMA)」の業績が好調です。
クリーマは、クリエイターがつくった作品を気軽に出品して販売できる、クリエイターと買い手を結ぶためのプラットフォームです。アプリのダウンロード数は1100万件。日本及びアジア最大級のグローバルハンドメイドマーケットプレイスとしてのポジションを確立しています。
ユーザーは、服やアクセサリー、インテリア、生活雑貨、アート作品に至るまで、作家やデザイナーが登録している1100万作品の中からお気に入りをEコマースで購入することができます。
昨年11月、創業10周年を機に東証マザーズに上場。2021年2月期の流通総額は前年同期比1.7倍の154憶円を達成しました。
クリーマの基本となる思想は、頑張っているクリエイターがきちんと評価される場をつくること。そのため当初から出店者の数を競うのではなく、クリエイターに信頼されるコミュニティをつくるために時間と手間をかけてきました。
また買い手も、「少しでも安く買いたい、ポイントを貯めたい」という人ではなく、クリエーションやモノづくりに関心の高い女性が中心。月に2千数百万人のユーザーが訪れています。
最近は、これまでオンラインでは身近でなかった伝統工芸品も人気に。特に家具や陶器、七宝焼き、鍋、やかんといった生活を豊かにするアイテムに注目が集まっています。
新型コロナウイルス感染拡大の影響で、女性の暮らしに対する価値認識は大きく変わりつつあります。ステイホームが長期化することで、毎日の生活を重視する女性が増え、クリーマのようなハンドメイドマーケットプレイスには追い風が吹いています。
クリエイターは、自分の作った作品を手軽に販売できて笑顔になり、買い手はお気にいりの商品を手に入れたり、クリエイターとのつながりができて笑顔になる。
そんな女性の笑顔の総和がクリーマの躍進を支えています。

みなさんこんにちは。和田康彦です。
「ゴディバ」といえば、女性が大好きなチョコレートの代名詞といってもよいくらい日本でも人気のブランドです。
そのゴディバが、今日2021年5月20日付日本経済新聞朝刊で一風変わった全15段広告を掲載していました。
ゴディバは95年の歴史をもち、世界100カ国以上で展開、日本では約300店舗を展開するプレミアムチョコレートカンパニーです。
ゴディバ ジャパンでは「We create Memorable Occasions of Happiness 私たちは、記憶に残る幸せな時を届けます」というミッションのもと、質の高い商品とサービスを提供しています。
老舗としての伝統を守りながらも、最近はギフト用だけでなく、ドリンクやソフトクリーム、コンビニスイーツなど気軽にゴディバの世界観を楽しめる商品を開発するなど新しい試みにも挑戦。2019年の売り上げは過去最高の436億円で、2010年比で3倍以上と快進撃を続けています。
このゴディバの成長を牽引するのが、弓道五段のフランス人経営者ジェローム・シュシャン氏です。
「幸せのつかまえかた」というキャッチフレーズで始まる今日の広告では、
シュシャン氏がまだ大学生だった38年前に福井県を訪れ、禅の文化に興味を持ち、永平寺の荘厳な佇まいに感動したこと。
そして今年久しぶりに福井を再訪し、シュシャン氏が改めて感じたことが書き綴られています。
福井は幸福度日本一の県といわれていますが、シュシャン氏は
「決して華やかな県ではないが、人に対するリスペクトを忘れずに代々受け継がれてきた歴史や技術や文化を大切にすること。
そして、そんな故郷の素晴らしさをこれからの世代にも伝えるように努力すること。一見平凡に見えるこんな静かな幸せこそが、実は長続きするこれからの新しい幸せなのだということを福井の人たちは知恵として知っているように思えました。
私たちGODIVAと福井県には共通点があります。福井が旅人さえも幸せにするようにGODIVAも味わってくださった全ての人を深い幸福感でいっぱいにしたい。
その根幹にあるものも同じ。人に対する愛と人生に対する敬意です。
私が福井を訪れるたびにシンパシーを感じる理由はそこにあるのだと思います」と締めくくられています。
新型コロナウイルス感染拡大によって、私たちの幸せの価値観も変わり始めているといってもよいと思います。
一見平凡に見える静かな幸せの提供こそが、これからの女性を笑顔にするキーワードになりそうです。
#幸せはすぐそばに

みなさんこんにちは。和田康彦です。
新型コロナウイルス感染拡大によって、昨年は食品の電子商取引(EC)元年といわれるほど、食品EC市場が大きく伸びる一年になりました。
2000年に創業したオイシックス・ラ・大地は、生鮮宅配で独自のネットワークや品ぞろえを拡充する一方で、同業の大地を守る会やらでぃっしゅぼーやを次々に経営統合することで成長してきました。
2021年3月期の連結売上は前年同期比41%増の1000億円。オイシックスだけでも一年間で約7万人の会員が増え、いまでは30万人以上の会員に愛されています。
●強みは全国4000軒の生産者とのネットワーク
オイシックスの強さの源泉は全国約4000軒の生産者と会員を直接結ぶネットワークにあります。
野菜や果物などは天候などにより収穫量が左右され、事業者にとっては生産計画を立てにくいという課題があります。
例えば作りすぎると廃棄しなくてはいけません。そこで同社は、全国4000軒の生産者から届く生産現場の状況や供給量の予測と購入者データを照らし合わせて、最適な需給システムを構築しています。
例えば、ニンジンが採れすぎた場合、過去の購入者データをもとに、ニンジン購入の可能性の高い顧客におすすめをすることで、できるだけ売り切るとともに、それでも余ればミールキットに利用することで食品廃棄率0.2%という驚異的な数字を実現しています。
また、収穫量が少なく市場に出回らない珍しい野菜も直接農家から仕入れ、他社との違いを打ち出しています。
さらに2013年7月には、必要量の食材とレシピがセットになった、主菜と副菜の2品が20分で完成するミールキット『Kit Oisix』を発売。調理時間を節約したいと考える働く女性から大きな支持を得て、シリーズ累計出荷数は8000万食(2021年3月末時点)を突破。同社の主力商品として、新たな市場を開拓しました。
●消費者の「おうち」が食関連ビジネスの主戦場に
2020年、新型コロナウイルス感染拡大によって、在宅勤務が広がり外食を控える消費者が急増することで、自宅でもレストランなどで味わえる本格的料理を宅配で注文する人や、自ら調理する人が増加。
消費者の「おうち」が食関連ビジネスの主戦場になりました。
同社も、本業の有機野菜の宅配をベースに、飲食店の味を食卓に届けるサービスや異業種とのコラボ、多様な食への対応、リアルな売り場の拡充など、巣ごもり需要の拡大を追い風にして事業を成長させてきました。
●飲食店の味を食卓へ
新型コロナウイルス感染拡大によって、食のライフスタイルは激変しました。特に居酒屋を利用する消費者は激減し、外食産業に大きな痛手をもたらしました。
オイシックス・ラ・大地では、コロナを機に外食産業との協業を加速。塚田農場を運営するエー・ピーホールディングスと資本業務提携し、3月には傘下の水産卸会社を子会社化。
のどぐろを使った炊き込みご飯など新たなメニューを開発して、同社の取扱い商品の拡充につなげています。
また、8月には大戸屋ホールディングスと業務提携。大戸屋の人気メニューを自宅で楽しめるミールキットを共同開発し、今後5年で共同事業を30億円規模まで拡大させていく計画です。
●異業種とのコラボで客層を拡大
2020年冬にはウォルトディズニージャパンと組んで、ミールキットを発売。ミッキーマウスやミニーマウスのカタチをしたハンバーグをつくる食材や道具が一緒に届き、子供と一緒に調理する時間を楽しめる、と話題になりました。
また、野菜の育ち方が描かれたランチョンマットやレンコンのきれいな切り方がわかるレシピ冊子を付属。「調理・盛り付け・配膳」すべてのプロセスで子どもが積極的に関わりたくなる要素を盛り込み、食育の事業領域を広げることにも注力しています。
●多様な食への対応
2019年10月には、米国のヴィーガンミールキット「Purple Carrot (パープルキャロット)」の提供を開始。アメリカでは健康意識や地球環境への関心の高まりからヴィーガン食市場が拡大しています。
ただ、アメリカでヴィーガンミールキットを利用している顧客のおよそ8割は「時々ヴィーガン」の食生活を楽しんでいる人たちです。
オイシックスでも、昨日はお肉を食べすぎてしまったから、今日はヴィーガンメニューを。お昼はイタリアンだったから、夜はヴィーガンメニューを。そんな感覚で「時々」ヴィーガンを楽しむ、という新しい選択肢の提供を日本でもスタートしました。
楽しく美味しく心と身体を整えられる新しい食の体験として、多様な料理ジャンルの一つの選択肢として、気軽に親しみ、楽しめるミールキットを提案することで未来の食文化を創造しています。
●リアルも拡充
2016年には、移動スーパーとくし丸を子会社化。地方の過疎地などを中心に、定期的に消費者の自宅近くを廻り生鮮品などを販売しています。2021年3月期の売上は前年同期比54%増の165億円。こちらの事業も高齢者からの支持を得て順調に成長しており、トラック数を現在の740台から早期に1000台に増やす計画です。
●オイシックス成長の背景にある時代や消費者の変化を読む力
食品宅配事業には、楽天やイオン、アマゾンジャパンなどが参入し、競争が激化しています。とはいえ、日本の食品EC化率はわずか3%。現在は市場を奪い合うというよりも市場を広げていく段階といえます。
オイシックスは、2000年の創業以来、時代の変化や女性消費者の心を読むことで成長してきました。
1990年代以降、欧米社会ではダイエットや健康・自然志向が高まります。
「外見はもちろん、内面から美しくなりたい」と考える女性が増加するなか、流行の先端を行くハリウッドスターたちはヨーガへ心酔し始め、ヨーガ・ブームが急速に沸き起こりました。
また1990年後半から、アロマ、ヒーリングなどの言葉が流行し自然派化粧品が見直され始め、2000年以降はLOHASという新しい潮流とともにオーガニックというカテゴリーのスキンケアが注目されるようになりました。
それに加え環境問題、食品の偽造、汚染問題などが後押しとなり、生活者の体に取り入れるものは(肌に対しても)食と同じ安全性を求めるべきという意識が芽生えはじめました。
このような女性の意識や価値観の変化を見抜いて、いち早く安心安全な農産品の宅配事業に参入したオイシックスはまさに先見の明があったといえます。
また、2013年7月に発売を開始したミールキット『Kit Oisix』は、働く女性の増加を先読みして開発された商品です。
内閣府が発表している男女共同参画白書によると2016年の共働き世帯数は1129万世帯。1980年と比較すると約1.8倍の増加となり、今後も増えていくことが予測されます。
また厚生労働省が発表している2016年国民生活基礎調査によると、18歳未満の児童を持つ母親が働いている比率は67.2%、約7割弱の母親が子育てしながら働いていることがわかります。
働く女性が増えるとともに、調理を簡便に済ませたい、でも手抜きと思われたくないと考える女性が増えていきます。主菜と副菜の2品が20分で完成するミールキット『Kit Oisix』は、そのような働く女性の潜在ニーズを先読みして見事成功した商品です。
オイシックスでは、時代の流れを的確に予測するとともに、会員から生の声を聞くことにも注力しています。
定期的にメールや電話で利用者に満足度や改善点を聞くほか、実際の顧客の家を訪問したり、利用者の子供を招いて試食会を実施したりしています。
例えば「カットした小松菜は、2~3cmが食べやすい」など、生の声がなければわからない経験を蓄積して独自商品を増やしています。
一方で、これまでに蓄積していた膨大な顧客データも活用しながら、顧客が「こういうモノが欲しかった」という商品を生み出すことを重視しているのです。
新型コロナウイルス感染拡大によって定着した「巣ごもり需要」やSDGsの浸透によって生まれてきた環境意識や食品ロスへの関心の高まりなど、女性を笑顔にするためには、常に消費者の変化を注視していくことが重要です。