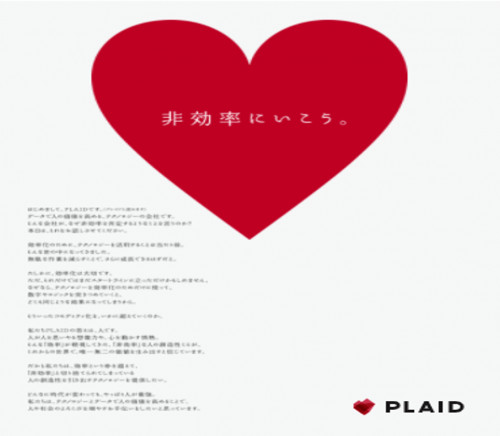体験消費時代のマーケティングヒント

みなさんこんにちは。和田康彦です。
コロナ禍の中で消費減速が続く中、ニトリホールディングスの業績は絶好調のようです。2020年3~11月期の連結営業利益は前年同期比約4割増の1200億円弱、売上高は5400億円程度と1割強増収、既存店売上高は11%増えたようです。(2020年12月9日日本経済新聞朝刊)。
背景には、新型コロナウイルスの感染長期化を受けて巣ごもり需要の裾野が拡大したことがありますが、同社ならではの、顧客ニーズの変化にきめ細かく対応する生活者視点マーケティングの成果が現れています。
例えば、春先は在宅勤務向けに横長でやや大型の机が売れていましたが、直近では、家の空きスペースを活用できる小型の机が好調です。また、長時間同じ体勢で座ってゲームをしていても疲れにくい椅子「ゲーミングチェア」の販売も伸びています。
一方で、忘年会や会食が減ったことで自宅での食事が定着し、皿やグラスなど食器や調理器具を新調する消費者が増えています。また、自宅に自分好みのワークスペースを作ったり、収納用具を充実させたりする消費者も増加しています。
さらに、おうち時間を心地よく過ごしたいと考える消費者の気持ちに合わせて、上質な革使ったソファを投入するなど、コロナ下で変化する消費トレンドを先取りした商品展開に力を入れ、リピーター獲得につなげています。ベトナムの自社工場では曲線を使ってデザイン性を高めた家具も開発しています。
冬場になってからは、発熱素材を使った寝具や部屋着「Nウォーム」シリーズも伸びており、自社ネット通販も5~6割増えているようです。
今回の新型コロナウイルスのような外的なショックが起きた時に企業の真の競争力が分かります。それは顧客に対してどのように独自の価値を提供できているのかということです。ニトリホールディングスも場合、製造・小売りに加えて物流も自社で手掛けており、新型コロナ下での電子商取引(EC)で強みを発揮しています。海外での商品開発力も温めて、長い時間をかけて水面下で培った競争力が、ニトリホールディングスの好業績を支えているといえます。
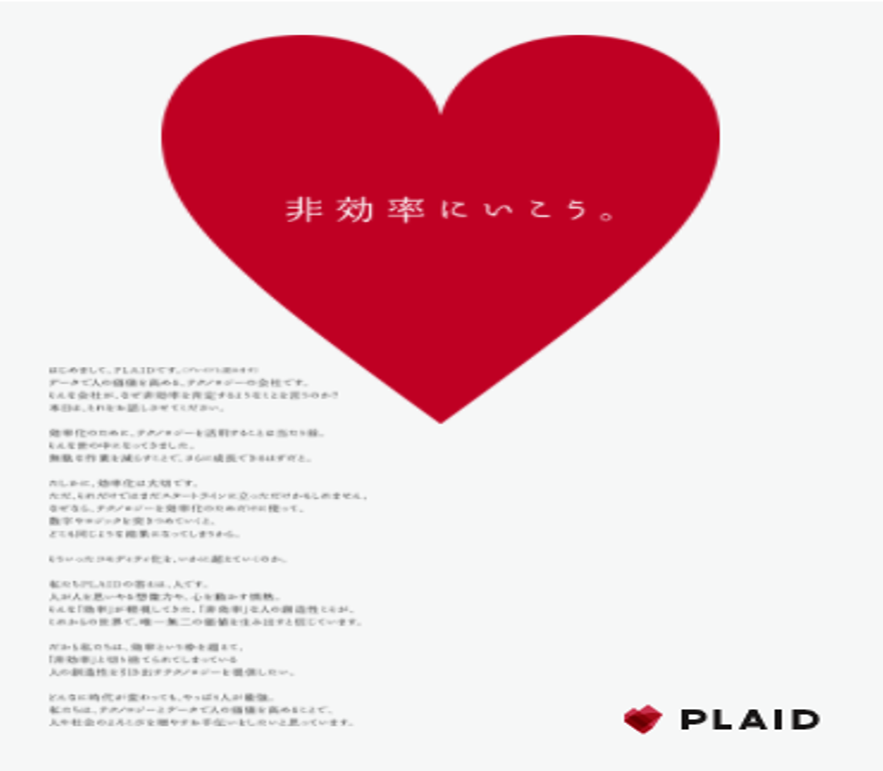
みなさんこんにちは。和田康彦です。
本日2020年12月17日付の日本経済新聞を見ていると「非効率にいこう。」というキャッチフレーズの全面広告が目に飛び込んできました。
どこの会社の広告だろう?と興味を持ってみると「PLAID」という社名が記されています。
そのまま、ボディコピーを読み進めていくと、この会社、本日東京マザーズ市場に上場するらしく、その記念広告であることがわかりました。
同社は、「データによって人の価値を最大化する」をミッションに掲げ、データやテクノロジーで人が本来持っている直感や創造力を引き出せる環境を実現し、その先に、あらゆる人がより良い体験を享受できる社会を目指している、今注目のテクノロジーの会社です。
テクノロジーといえば効率を追求するのが当たり前の世界ですが、今回なぜ「非効率でいこう。」という真逆のメッセージを発信しているのでしょうか。
いかにそのメッセージの一部を抜粋させていただきました。
「たしかに効率化は大切です。
ただそれだけでは、まだスタートラインに立っただけかもしれません。
なぜなら、テクノロジーを効率化のためだけに使って
数字やロジックを突き詰めていくと、
どこも同じような結果になってしまうから。
そういったコモディティ化を、いかに超えていくのか。
私たちPLAIDの答えは、人です。
人が人を思いやる想像力や、心を動かす情熱。
そんな「効率」が軽視してきた、「非効率」な人の創造性こそが、
これからの世界で、唯一無二の価値を生み出すと信じています。
だから私たちは、効率という枠を超えて、
「非効率」と切り捨てられてしまっている
人の創造性を引き出すテクノロジーを提供したい。
どんなに時代が変わっても、やっぱり人が最強。
私たちはテクノロジーとデータで人の価値を高めることで、
人や社会のよろこびを増やすお手伝いをしたいと思っています」
このところ、デジタルシフトやDX(デジタルトランスフォーメーション)が叫ばれていますが、テクノロジーはあくまでも人の創造性を引き出すための道具であることを忘れてはいけませんね。
久しぶりに、すてきなメッセージの広告に出会いました。これからもPLAIDという会社に注目していきたいと思います。

みなさんこんにちは。和田康彦です。
前回と前々回は、今注目されているD2C(Direst to Consumer)ビジネスについてお話ししてきました。
ニューノーマル時代に注目されている「D2Cビジネスモデル」とは?http://womanmarketing.net/info/3652998
「サスティナブル×D2C× サブスク」モデルで急成長中のブランド「パブリック・グッズ(PUBRIC GOODS)とは?http://womanmarketing.net/info/3653445
◆D2C(Direst to Consumer)とは
改めておさらいしておくと、D2C(Direst to Consumer)とは、小売店などの仲介業者を介せず、直接商品を顧客に販売する新たなブランドの販売手法のことでした。
基本的にリアル店舗をもたず、ネット通販を中心に展開することで、店舗運営のコストを圧縮し、浮いた費用を商品開発やマーケティングに投資します。
その上で、デジタル上で顧客とつながり、意見や要望を吸い上げて商品を改善・進化させていくのが大きな強みとなるビジネスです。
◆ニッチ分なニーズを捉えて勝負する「マイクロD2C」
今回は、2021年のトレンドとして注目されている「マイクロD2C」についてご紹介させていただきます。
これまでもお話ししてきたように、D2Cには、小さな会社ならではの機動性を活かし、多様化する消費者のニッチなニーズを捉えて成功しているブランドが多いのが特徴です。
例えば、3万通りの組合せから一人ひとりのお客さまに適したシャンプーとコンディショナーをお届けする「MEDULLA(メデュラ)」、胸の大きい女性向けアパレル「overE」、お客さまの生活習慣に合わせ25種類のレシピの中から適したスムージーを展開する「Green spoon」など、大企業では事業規模の面からも参入できないような未開拓の市場でお客さまの支持を得ているブランドが多く生まれています。
◆マイクロD2Cを支援するプラットフォームが充実
ところで、D2Cビジネスが注目されることで、このところD2Cのものづくりや物流、ECシステムなどを支援するプラットフォームが出そろってきました。これにより、小さな会社やでも個人でも、その強みを活かした事業展開が可能になります。2021年は、まさに、小さなD2Cが花開く「マイクロD2C」元年になることが予測されます。
例えば、アパレル製造では、「シタテル」という会社が、デザイナー、生地メーカー、工場など洋服づくりに携わる約850のパートナーをネットワーク化。ブランドオーナーは、シタテルのスタッフとオンライン上で相談しながら素材選びや洋服のデザインをすることができます。
また、化粧品では、「サティス製薬」がD2Cを支援 。発注ミニマムロットを300個にまで減らすことで、在庫リスクが軽減でき、参入しやすくなりました。
物流面では、「オープンロジ」が、固定費なしで商品1点から使える従量課金制の物流サービスを展開。入庫から在庫管理まですべてオンライン上で完結できます。
さらに、「BASE」などのECプラットフォームを利用すれば、誰でも無料で数分もあれば簡単に商品の販売をスタートすることが可能です。BASEは、サイトデザインの自由度が高く、ブランドの世界観に合わせたネット通販が可能になります。また、決済面をはじめとした運営サポートが充実しているので、初めての方にはおすすめのプラットフォームです。
誰もが簡単に参入できるようになったD2Cビジネス。2021年はあなたの企業でもぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

みなさんこんにちは。和田康彦です。
前回は、ニューノーマル時代になぜD2Cビジネスモデルが注目されているのかについてお話しさせていただきました。http://womanmarketing.net/info/3652998
今回は、今アメリカで急成長中のD2Cブランド、「パブリック・グッズ(PUBRIC GOODS)の特徴についてご紹介させていただきます。
同社は、2016年、モーガン・ハーシュ(Morgan Hirsch)とマイク・ファーチャック(Michael Ferchak)が共同で創業。良質でエコ、ミニマルな商品を中間マージンを省いたD2C(Direst to Consumer)で販売するビジネスモデルを強みとしています。当初は、ハウスホールド(家庭用品)とパーソナルケア(個人のグルーミング用品)からスタートしましたが、2017年には、クラウドファンディングで約7000万円を調達。その後2019年にも、クラウドファンディングで約4300万円調達し業容を拡大。現在は、食品カテゴリーを追加し品揃えを充実させています。
◆パブリック・グッズ(PUBRIC GOODS)6つの特徴
① 会員制のサブスクリプションモデル
年会費59ドル(約6100円)を支払った会員だけが商品を購入できるサブスクリプション(定額制)メンバーシップサービスを採用。
② リーズナブルな価格でサスティナブル商品を販売
安定的な利益を見込めるサブスクスタイルにすることで、エコ商品は高いというイメージに反し、リーズナブルな価格でサスティナブルな生活用品を販売。
③ Z世代が支持
サスティナブルで、ノントキシック(毒性のない)、オーガニックな商品を好むZ世代(1996年から2010年までに生まれた世代)が支持。
④ コロナ禍のもとで成長
ニューヨーカーは、物を大量に消費するより、SDGs(国連サミットで採択された持続可能な開発目標)に沿ったサスティナブルな暮らしにシフト。20年2月以降、会員数は2倍に、売り上げは5倍に急増。
⑤ 250種類の豊富な品揃えとリーズナブルな価格
パラベンや硫酸塩などの有害な化学物質を含まないヘア&ボディー用品をはじめ、詰め替え用のレフィルも豊富に用意。また、再生紙やバンブーを使用したツリーフリー(木から採取されるのではない)紙でできたトイレットペーパーやキッチンペーパー、生理用ナプキン。食品はオーガニック&フェアトレードが基本です。
⑥ インテリアの邪魔にならないミニマルなデザイン
写真のようなシンプルなボトル類のデザイン。素材には、環境への悪影響を低減するため、プラスチックの使用は可能な限り避け、サトウキビベースのバイオプラスチックに頼っているものもある。
サステイナブルな商品をリーズナブルな価格で提供する同社の公式サイトでは、「地球を守るためにスーパーヒーローになる必要はない。私たちの小さな選択が大きなインパクトをもたらす」「私たちが直面している問題は、使うことを選んだ商品による結果だ」などのメッセージを発信。「サスティナブル」「健康」「美しい」の3つをブランドプロミスとして掲げています。
今年からは、全米に展開する大手ドラッグストチェーン「CVS」と提携し、一部店舗でテスト販売も開始。更なる成長を目指しています。
地球環境問題に消費者の関心が高まる中、サスティナブルなライフスタイルを提供する「パブリック・グッズ(PUBRIC GOODS)」からは、社会的意義に配慮したこれからのブランドのあり方が学べます。

みなさんこんにちは。和田康彦です。
このところ日本でも注目されているD2C(Direst to Consumer)ビジネスをご存知でしょうか。
D2C(Direst to Consumer)とは、自社で企画・製造した商品を自社サイトで直接販売するビジネスモデルのことです。
◆D2C(Direst to Consumer)ビジネスの特徴
2000年代後半から米国を中心に、スタートアップ企業が展開するビジネスモデルとして勃興。中間流通をなくしてコストを抑えるのは従来のメーカー直販と同じですが、SNSを通じて消費者と交流し、ともにブランドを作り上げているのが特徴です。最近では、ネット販売で一定の支持を得て直営店を出すケースも増えてきています。
また、D2Cのビジネスモデルは、世界観とストーリーテリングを武器とし、新しい競争優位のカタチを構築しています。つまり、これまでの伝統的なブランドのように、機能やモノのよさだけを売りにしないことも強みの一つです。
また、自社サイトにファンが集まる仕掛けを作り、顧客に商品企画やマーケティングに参加してもらい、商品としての「モノ」とブランドをともに育てる体験の「コト」の両方を売りながら、顧客と長く付き合うのが特徴といえます。
◆日本で今D2Cビジネスが注目されている背景
新型コロナウイルス感染症拡大によって生活者の意識や行動が一変し、企業のマーケティング活動は変革を余儀なくされています。また、移動や接触が制限される「新しい生活様式」の社会では、デジタル化やEC化への早急な取り組みが生き残りの大きな鍵となっています。
さらに、人口減少社会の中では、既存顧客のLTV(顧客生涯価値)向上に焦点を絞り、長期的な関係性の構築に向けて、顧客基点の商品体験の創出や継続的な価値提供が重要な戦略になっています。
そのような背景の中で、「顧客基点」を重視するD2Cビジネスモデルを積極的に取り入れていくことが、アフターコロナ時代の生存戦略として非常に重要になってきているわけです。
◆顧客基点(生活者視点)を最も重視するD2C(Direst to Consumer)
D2Cモデルは、商品開発、売場設計、プライシング、コミュニケーションなど事業のタッチポイントすべてを顧客体験を軸とした「顧客基点」で見直し、従来モデルとは根本的に異なった事業や組織として設計されています。
また、顧客基点を重視するD2Cは直販モデルを採用することで、サプライチェーンに関わる中間コストを削減。従来発生していた廃棄コストや中間マージンなどを削減しやすくなり、顧客が欲しい製品を適正価格で提供できるようになります。
また、顧客像や課題を事前に把握できているので、過剰な宣伝をしなくても顧客獲得の効率は向上しやすく、広告費を削減できる可能性があります。さらに、顧客の意見を傾聴することで、どんな商品を作ればいいのか、どの程度の需要があるのかが予測しやすくなるというメリットもあります。
このように、ロイヤルティーの高い顧客と共にオンリーワンのブランドを作り上げていくことがD2Cモデルの本質であり、顧客体験をとことん磨いていく思想とそこに投資するための原価構造の変化こそが、D2C型ECマーケティング戦略のポイントといえます。
顧客とつながり続けることを最も重視するD2Cでは、SNSで顧客とつながり続けて、コミュニケーションを最適化していくことこそが重要な戦略になります。顧客とつながる手段は多数ありますが、中でもSNSは企業と生活者がダイレクトにつながり続けることが容易で、顧客にとっても最も身近で手軽なツールといえます。
従来、接客などのオフラインで提供していた情報やその質も、ライブ配信やチャットの活用などで、オンラインで購入検討する人にとっても有益な情報になるように、コンテンツ化することが求められています。今後は、SNSで、共感や応援で自ら能動的につながってくれている顧客に情報を直接配信できる価値はこれまで以上に高まることが予測されます。
従来型EC事業者であってもD2C的顧客基点マーケティングのエッセンスを積極的に取り入れていくことは、顧客の商品やブランドへのさらなる愛着醸成につながり、結果的にLTVが向上していきます。
マス市場ではなく、ニッチな分野でオンリーワンを目指すD2Cビジネスモデル。あなたの会社でも新規事業として考えてみてはいかがでしょうか。