体験消費時代のマーケティングヒント

みなさんこんにちは。和田康彦です。
▪企業が経営不振に陥る2つの要因
企業が経営不振に陥る要因には、①企業内部に原因がある内部要因と②景気や立地の変化、競合店の出店など外からの影響が原因の外部要因の2つの要因があります。
とはいえ、不振企業の8割は企業内部に要因があるといわれています。
内部要因の中でも最も大きなものが、経営者自身の「経営に対する情熱の欠如」です。つまり、経営者や経営幹部の「あきらめシンドローム」が自ら経営不振を招いているのです。
「経営に対する情熱」と聞いて、あなたはどんなことを思い浮かべますか。
「売上をあげたい!」「利益を今の倍にしたい!」「新規顧客を毎月100人増やしたい!」など、数値目標を達成することを思い浮かべた方も多いと思います。このような大きな数値目標の達成にロマンを感じる経営スタイルも決して間違っているわけではありません。
ただ、顧客中心マーケティングを実践していく上での「経営に対する情熱」とは、「顧客に対する貢献点をどのように高めていくのか」ということであり、「自社が持つ顧客への貢献点を知って磨いていくこと」に他なりません。
ところで、「あなたの会社やブランドが提供する顧客への貢献点は何ですか?」と問われたとき、即答できるでしょうか。
顧客への貢献点こそ、あなたの会社やブランドの存在価値であり、顧客にとってのベネフィットです。
業績不振の要因を突き詰めていくと、自社の顧客に対する貢献点が時流の変化に伴って顧客に支持されなくなったことが浮かび上がってきます。
▪モノが売れない時代の顧客への貢献点とは
特に最近はモノ溢れの時代になり、単に良い品質の商品を売っているだけでは顧客の心を充たせなくなっています。
今の消費者の最大の関心ごとは、「自分の限られた時間をいかにワクワク過ごせるか」ということにあるといわれています。
心の豊かさを得られるのなら、お金も時間も労力も考えることや気を使うことでもどんどんエネルギーを注ぎこみたいと考えているのです。
反対に、心が豊かにならないただ生きていくだけの消費にはできるだけエネルギーは使いたくないというのが本音です。ただ生きていくだけの消費なら、安い方がいい、買い物に時間をとられたくない、あれこれ考えるのはいや、店員や周りの人にに気を使いたくないというのが今の消費者の心の内です。
ですから、「顧客の心を豊かにする」という志を持ち、自社の顧客に対してどんなことで貢献できるのか、を改めて問い直すことが必要になってきているのです。
例えば小売業であれば「価格と価値のバランス」、つまり、グッドプライス(最良の価格)、グッドMD(素晴らしい品揃え)、グッドクオリティ(最高の品質)が重要であることはどんな時代でも不変の価値です。
ただ「顧客の心を豊かにする」という視点で見た場合、顧客に最高の気分を味わってもらうためのグッドサービスや顧客の感性を刺激するグッドセンスの提供が重要になってきています。
さあ、あなたの会社でも、「心の豊かさを求めて自分の人生をよりよいものにしたい」と考える顧客のために、具体的にどんなことで貢献できるのかを問うていきましょう。

みなさんこんにちは。和田康彦です。
顧客中心マーケティングは、常に顧客の立場に立って考えて、顧客が幸せと感じる体験を提供し続ける活動です。
その結果、顧客の心の中に「好き」という感情が生まれ、企業やブランドのファンになってもらうことを最終目標にしています。
つまり、経営者もマーケターも顧客の「好き」という感情をもっと大切にしていかなければいけません。
人間は決断するとき、まず感情で決めているものです。ロジックは、実は後から考えていたりするものなのです。ですから、「好きかどうか」は、お客様から選んでもらうときの絶対条件なのです。
このようにブランディングやファンづくりをしていく上で、人間の本質的なところに訴えかけることはとても重要です。
例えば、私はスターバックスが大好きなんですが、実は社会人になったころスターバックスのコーヒーを持って歩いていると自立した社会人になったような気がして妙に自信を持てた、という体験が今のスタバ好きの原点になっているような気がしています。
スターバックスでは、現在もワクワクするような新商品を次々に開発し、地域や街の特徴に合わせた独自の店舗を展開。生活様式の変化に合わせたデジタル施策を拡充し、私たちに常に新鮮で心地よい体験を提供してくれています。
つまり、常に顧客の期待を超え、時代の移り変わりを捉え、お客様一人ひとりに寄り添った体験を提供し続けることで、多くの「スタバ好き」を生み出しリピーターを増やしているのです。
このように、「好き」という感情こそが行動のトリガーになり、モチベーションにもつながります。知名度や認知してもらっているかということももちろん大切ですが、いろいろな選択肢に溢れた現代は、「好きかどうか」ということが、顧客との関係性を築くための前提となるのです。
顧客から選ばれるのも、顧客がファンになるのも、顧客に使い続けてもらうのも、顧客と顔なじみになるのも
顧客の「好き」という感情がベースにあります。
今や、品質だけで顧客の購買意欲を掻き立てることは難しくなってきており、それよりもブランドとしての情報発信や顧客とのコミュニケーションをとることが重要になってきています。
そのためには、企業は「カスタマーハピネス」の実現を第一に考え、誰に何を伝えたいのか、その結果どういう存在になりたいのか、そのためにはどう伝えればよいのかという順番で考えることが必要です。
顧客との接点すべてが、顧客の心の中にブランドイメージを作っていきます。
ウェブサイトのビジュアルデザインはもちろん、SEO対策も広告もチラシもメールもSNSもブランディングの一部です。
サイトの新規立ち上げもリニューアルも写真撮影も動画制作も、顧客に対するすべての発信は自社のブランドを顧客から好きになってもらうことが最終目的なのです。
ところで、あなたの会社やブランドが顧客から選ばれる理由は何でしょうか。
技術や品質、価格や納期など大切なことは言うまでもありませんが、今お客様が求めているのは、日々の暮らしを向上させることであり、しいては心豊かに暮らすことなのです。
つまり、あなたの会社やブランドの商品やサービスを購入することで、どのような精神的ベネフィットを得られるかということが、現代の消費者にとっての最大の関心ごとなのです。
スターバックスが、老若男女を問わず多くのお客様から支持されているのは、単にコーヒーが美味しいという理由だけでなく、親しみのある接客であったり、ワクワクする新商品との出会いであったり、1人の時も友達と一緒の時もリラックスした時間を過ごせるという精神的なベネフィットを提供し続けているからです。
顧客中心マーケティングの最終ゴールは、あなたの会社やブランド独自の精神的ベネフィットを提供し続けていくことにあります。

みなさんこんにちは。和田康彦です。
企業が持続的に成長していくためには、常に顧客の立場に立って、顧客にどんな価値を生み出せるのかを考え続けていくことが重要です。
▪ZOOMのカスタマーハピネス経営に学ぶ。
新型コロナウイルスのパンデミックにより、全世界的に使われるようになったオンライン会議ツール「Zoom」。
同社の創業者でCEOのエリック・ユアン氏は、「もし従業員が幸せを感じていなければ、顧客もそれを感じとり、幸福感を感じることはできない。」と断言します。
そして、「CEOである私の最優先事項は、従業員に幸福感を持たせ、彼らがその幸福感を顧客にも届けられるようにすることだ。」と、顧客中心マーケティングを実践してくためには、従業員の幸せ感を育てることが最重要課題であることを力説しています。
ZOOMにとって、経営の中核的価値観は「カスタマーハピネス」であり、カスタマーハピネスを実現するためには、従業員幸福が前提になければならないという強い考え方が根底にあるわけです。
同社がカスタマーハピネス経営を実践する上で最重要視していることは、「すべてのことを顧客の視点から見る、考える」ということです。
そして次に大事にしていることが、「あらゆることをオープンにして透明性を保ち、信頼性を築いていくこと。そのために上手にコミュニケーションをとっていくこと」です。
3番目に大切にしていることが、「顧客を大切にする、会社を大切にする、チームメイトを大切にするという企業文化」を育てていくことです。
つまり、「従業員が幸福感を感じられるようにし、皆で力を合わせて企業として顧客を幸せにしていく」ことが、ZOOMの企業文化であり、そのためにCEOの役割があると考えているのです。
エリック・ユアンCEOは、毎日顧客とのミーティングに参加。顧客からのフィードバックを募り、話を聞き、どこに問題を感じているかを理解して、何を変えれば顧客にもっと価値を提供できるのかを考え続けているそうです。
目標は、対面でのミーティングよりも、もっとより素晴らしい体験を提供すること。ZOOMミーティング相手とハグできる、相手との親密さを感じられる、AIを使ってリアルタイム翻訳ができるなど、顧客の立場に立ったアイデアが、次なるZOOM躍進の原動力になりそうです。
顧客中心マーケティングの基本は、「顧客の立場に立って、顧客が喜ぶことを創造していくこと」です。あなたの会社でも、顧客中心マーケティングを経営の基本において、顧客幸福を追求していきましょう。それが成長の第一歩となります。

みなさんこんにちは。和田康彦です。
▪松下幸之助の「事業は人なり」
パナソニックを創業し、一代で世界的企業へと成長させた松下幸之助氏は、「事業は人なり」が口癖だったといいます。
どんなに素晴らしい技術やノウハウがあっても、どんなに優れた機械や設備があっても、どんなに立派な組織があっても、人が育っていなければ事業は発展しないのだと。この「人づくり大事」の考え方は、松下幸之助の経営に一貫しているものでした。
米調査会社ギャラップが2017年に実施した調査によると、日本は士気が高く熱意あふれる(従業員エンゲージメントの強い)社員の割合は6%で、調査対象139カ国中132位でした。2022年の同調査でも、その割合は5%で、調査対象129カ国中128位と低い結果に終わっています。
一方、GAFAM(IT企業の雄である5社(Google、Amazon、Facebook、Apple、Microsoft)の頭文字を取った呼び名)を生んだ米国の、士気が高く熱意がある従業員エンゲージメントの強い社員の割合は34%と世界の中で突出しています。
この調査結果からも、デジタル時代の競争力の源泉は、工場や店舗といった有形資産ではなく、人が持つアイデアやノウハウ、ブランドなどの人的資産=無形資産に移ってきていることが分かります。
人的資本とは、人間が持つ知識やスキルなどを資本とみなしたものであり、教育や訓練などで蓄積され、生産性の向上やイノベーションの創出につながっていくものです。
つまり、経済のデジタル化やグローバル化の進展で、優秀な人材を確保したり育成できるかが、企業の競争力を大きく左右するようになってきているのです。
中小企業にとっても、これまでのように人をコストとみて人件費を削るのではなく、人に投資して付加価値を伸ばしていくという考え方抜きでは今後成長していくことはできません。
▪従業員エンゲージメントを向上させるメリット?
それでは、従業員エンゲージメントを高めることで、企業にとってどのような利点があるのでしょうか。
まず、士気が高く熱意がある従業員が増えることで、アイデアや創意工夫が生まれやすくなり職場の活性化につながります。その結果、業績への好影響も期待できるでしょう。
次に、従業員エンゲージメントが高いということは、従業員が自分の仕事に対して意義を感じ、こだわりを発揮しやすい状態です。当然ながら、従業員の取り組み方が前向きになれば、提供する商品やサービスの品質も高まりやすくなり、結果として顧客の満足度につながり、企業としての信頼度もより向上させることが可能です。
そして、業員エンゲージメントが高まることで、従業員は自組織への不満が少なくなり、帰属意識や愛社精神が高まります。その結果離職率の低減も期待できます。
▪従業員エンゲージメントを高めるためにやるべきこととは?
従業員エンゲージメントを高めるためには、具体的にどのような取り組みをすればよいのでしょうか。
まず、企業理念・ビジョンを浸透させることが重要です。「顧客や社会に提供できる価値は何か」を明らかにすることで、従業員からの賛同が集めやすくなります。経営者が熱い想いを持って、地道に浸透させていく活動が大切になります。
次に、納得性の高い人事評価制度に改善していくことが有効です。人は正当な評価を得られない職場では、組織に貢献しようというモチベーションが沸きません。評価への納得度を上げることで、従業員の仕事への積極性や意欲を高めることが可能です。
そして、上司が部下の意見をできる限り承認したり、信頼して権限を委譲したりするなど、承認・称賛の文化をつくることも従業員エンゲージメントを高めるポイントです。例えば、社長賞やMVPをはじめ定期的に表彰の場を設けることで、従業員の意欲も高めやすくなります。
さらに、社内コミュニケーションを活発化させ、従業員同士の関係性を深めることも大切です。例えば、定期的なランチミーティングや従業員同士が褒め言葉を紙に書いて贈り合う「褒めカード」などが有効です。
また最近では、従業員の成長を支援できるようなキャリア開発の施策を取り入れる会社も増えてきました。例えば、マイクロソフトでは、従業員18万人の内、月平均10万人が同社の教育プログラムにアクセスしているそうです。中小企業では、従業員にオンラインセミナーを受講させたり、積極的に展示会等に参加させることも効果的です。
その他、従業員が健康的に働けるような環境や制度の見直し、上司のフィードバック能力を高めることも大切です。
顧客中心マーケティングを実践していくのは、まさに従業員一人ひとりです。従業員のやりがいや幸福度を高めていく経営こそが、顧客中心マーケティングの要となります。あなたの会社でも、従業員を大切な資本と考え、従業員の幸福を実現する経営に舵を切っていきましょう。
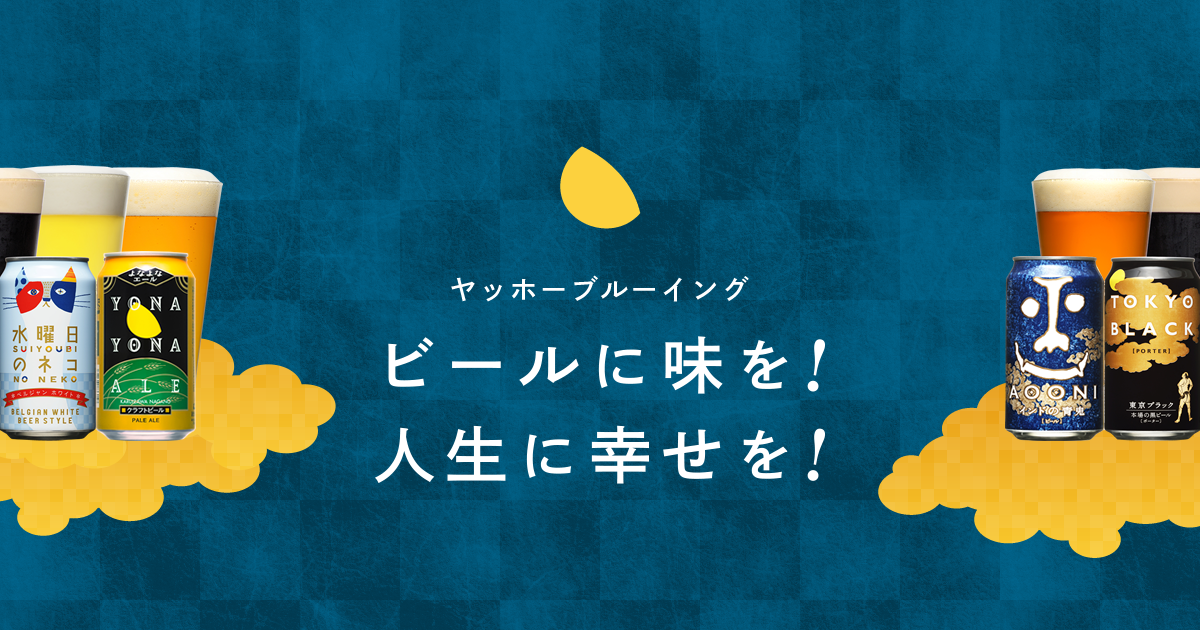
みなさんこんにちは。和田康彦です。
顧客中心マーケティングを実践していくためには、年齢や役職に関係なく自由闊達に意見を言い合える組織風土の醸成が重要です。
米グーグルが2012年に始めた調査では、生産性の高い組織には、一人ひとりの従業員が長所を発揮し、安心して意見が言い合える土壌があることを発見しました。
つまり、生産性の高いチーム作りのキーワードは「心理的安全性」であることを突き止めたわけです。
そのためには、マネージャーは良い聞き役になり、時には自身が弱みを部下にさらけ出すことで風通しの良い雰囲気をつくり出すことが重要になってきます。
リクルートが2021年10月に行った、会社員の職場におけるコミュニケーション量の変化についての調査結果を見ると、調査対象者の37.6%が以前より「減った」と回答。一体感や仲間意識が減少した人は30.4%、職場の仕事の効率性や生産性が低下したと答えた人も25.2%に上りました。
コロナ禍のリモートワークで、リアルなコミュニケーションが失われたことが背景にあるとは思われますが、リーダーもコロナ禍の対処に明確な答えを持っているわけではなく、先行き不透明な時代こそ、全従業員が意見やアイデアを出し合えるフラットな組織づくりが大切になってきます。
●ヤッホーブルーイングの「雑談朝礼」
クラフトビールファンから「よなよなエール」などが支持され、18年連続増収を続けるヤッホーブルーイング。マスプロモーションではなく、長年続けているファン向けのイベントなど、時代の流れ、消費者ニーズに応じた独自の施策によって認知度を広げ、新規顧客を獲得、そしてファン育成を続けてきました。
コロナ禍においてもSNSを活用したオンラインイベントなどのファンコミュニケーションを継続。環境の変化に応じて綿密にニーズを汲み取り、ひたむきにファン作りに取り組んでいます。
同社は2000年代、意思疎通の悪さから社員の半数が会社を去って行くなど、深刻な経営危機に直面しています。
その後、従業員同士のコミュニケーションや信頼関係を醸成するために、休日の出来事や趣味などを自由に30分間話し合う「雑談朝礼」をスタート。
その結果、年齢や役職に関係なく意見を出し合う土壌が育ち、新たな意見やアイデアが生まれやすくなったといいます。
例えば、部署の垣根を越えて集まった意見をもとに実現したイベント出店。ビール原料のホップの香りを顧客に体験してもらうとともに、製造工程の動画を流し、ビール完成までをイメージしてもらうことで、行列が出きるほどの人気イベントになっています。
このように、顧客中心マーケティングを実践していくためには、全従業員が顧客のために活躍できる環境づくりが重要になっています。そのためには、従業員同士がお互いに信頼できる基盤がなくてはいけません。
