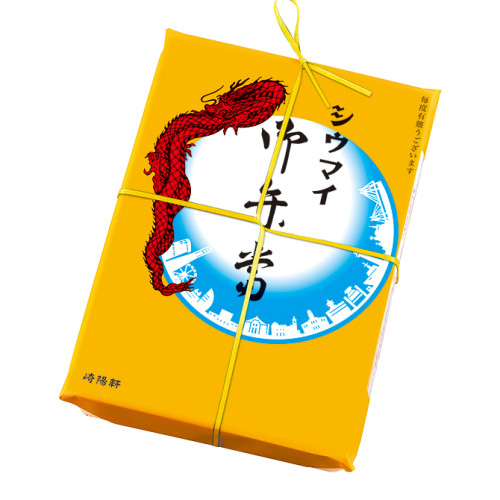体験消費時代のマーケティングヒント

みなさんこんにちは、マーケティングコンサルタントの和田康彦です。
私が提唱する女性客に好きになってもらうマーケティングとは、あなたの会社の一番の魅力でお客様を引き寄せ、離さない、お客様とつながり続ける仕組みづくりです。
今回は、みなさんもよくご存じの「シウマイ弁当」で有名な崎陽軒さんをケーススタディにして、半世紀以上もお客様に愛され続けている秘訣について学んでいきましょう。
▪1928年横浜名物、冷めても美味しい「シウマイ」が完成
崎陽軒は1908年、横浜駅(現在の桜木町駅)構内での営業許可を受けて、寿司や餅、サイダーなどのを販売する売店からスタート。1923年には法人化して、合名会社崎陽軒となりました。
以降、横浜駅で弁当などを販売していましたが、売上は一向に伸びません。なぜなら、東京からの乗客の多くはすでに駅弁を購入しており、反対に、上り列車の乗客も、あと少しで東京に着くタイミングなので駅弁は買わないからです。
そこで初代社長の野並茂吉氏は頭を悩ませた末、横浜でしか手に入らない“キラーコンテンツ”があれば、乗客も買ってくれるのではないかと考えました。当時、横浜には名産品と呼べるものがなかったため、そこから名物づくりが始まったといいます。
当時、南京街(現在の中華街)の店で突き出しとして提供されていた焼売に目をつけた茂吉氏は、これを名物にしようと決意。点心職人をスカウトし、1年かけて冷めてもおいしい「シウマイ」を開発しました。1928年のことです。
その後、太平洋戦争を経て1950年に転機が訪れます。販売促進施策として、横浜駅のホームから乗客などに向けて赤い服を着た女性がシウマイを売り歩く、いわゆる「シウマイ娘」を誕生させたのです。
これが話題を呼び、毎日新聞に連載された獅子文六の小説「やっさもっさ」に登場。映画化もされて、全国に横浜名物・崎陽軒のシウマイが知れ渡るようになりました。当然、売り上げも一気に伸長します。
その後1954年にはシウマイ弁当を開発。半世紀以上も経った今でも同社の看板商品として、横浜を代表する駅弁の座を守っています。
▪昔からの製法、デザインを堅持
黄色い掛け紙がかかった経木の器にシウマイ5個に唐揚げ、たけのこ煮などのおかずを盛り付けたシウマイ弁当(860円税込)は、キオスクほどの大きさの横浜駅中央店では1日700食を売り上げ、東海道新幹線の東京駅や新横浜駅などでは出張族の定番の味です。
シウマイの材料には、オホーツク産の干しホタテ貝柱を使用。俵型ご飯(小梅、黒胡麻)は、もちもちした食感を保つために蒸気炊飯方式で炊き上げています。
折り容器は、アカマツやエゾマツなどの天然木を使った経木のままでそのサイズも変えていません。そしてシウマイの箱の中に入る48種の絵柄を持つ磁器製しょうゆ入れ「ひょうちゃん」も馴染みの顔のままです。
そして、シウマイの具材や調味料は、飽きがこないようにあえてシンプルな味に保っています。一度おかずの具材の唐揚げをエビフライに変更したところファンから抗議が殺到したため、元に戻したというエピソードが物語っているように、時代が変わっても昔ながらの姿を大切にしているところが、時代を超えて多くのファンから愛されている秘訣といえます。
▪「ナショナルブランドではなく、ローカルブランドを目指す」
崎陽軒の経営理念のひとつに、「崎陽軒はナショナルブランドを目指しません。真に優れた『ローカルブランド』を目指します。」という一説があります。
例えば、アルゼンチンタンゴは、元々はブエノスアイレスの港町で生まれた民族舞踏ですが、その真に優れた音楽性が受け入れられて、今では全世界で知られるようになりました。このようにローカルブランドに徹することでナショナルブランドを越えるブランドとして存在できる、という考え方が根底にあります。
▪地域に密着した売り方でファンを創造する
実は、シウマイ弁当には駅弁とは別の顔もあります。地域のイベントや企業・団体の注文でも高いシェアを持っており、これも横浜で愛されている理由なのです。
例えば選挙の日には投開票所や事務所などに配送。イベントが雨天中止となったときなどに当日朝のキャンセルも可能なため、運動会などで関係者向け弁当の注文が圧倒的に多いといいます。
横浜スタジアムでの野球試合開催時や、パシフィコ横浜での大規模イベント開催時にも特別な販売体制をとり、従業員が総出で販売にあたります。
販売面で機動力が発揮できる舞台裏には、東京都と横浜市に計3カ所ある工場からの製造・配送体制の工夫があります。機械化している工程はシウマイ製造など一部で、弁当の盛り付けはほとんどが人の手だのみのため、時間ごとにシウマイ弁当と他の弁当を作り分けることも可能なのです。
一方、新型コロナの影響で同社の経営環境は一変しました。鉄道、特に新幹線での移動が急減して大人数が集まるイベントの需要もストップ。こうした中で、同社を支える柱となったのは地域の根強い支持層だったのです。仕事帰りに購入して家庭で食べてもらうなどの需要が拡大。従来からのシウマイファンが強い味方になり、同社の経営を支えてくれました。
崎陽軒では盛り付けを手作業で行う機動力を活かして、春夏秋冬、その後追加した「初夏」を含めた5種類の季節弁当も販売。毎年おかずを見直して楽しめる作りとしたほか、母の日やハロウィーンなどイベントに関連した限定商品も販売しています。
横浜ゆかりで崎陽軒のファンだった故・桂歌丸さんにちなんだ弁当や、サッカー・J1の横浜F・マリノス、JR相模線などとのコラボ弁当も投入。2021年には季節弁当を含めて定番商品に加えて30種類以上を販売しています。同社のファンはシニア層割合が高いのですが、外部とのコラボによって新たな客層拡大も狙っています。
▪地元ファンが熱心に訪れる工場見学
「崎陽軒 横浜工場」では、2003(平成15)年のリニューアルオープン以降、崎陽軒の安全・安心なものづくりをお客様に伝えたい思いから「工場見学」を実施しています。
工場では、シウマイ・弁当の「製造ライン」を見られることはもちろん、「駅弁の歴史」や「シウマイ弁当のひみつ」なども学ぶことができます。また見学の最後には、できたてのシウマイ、シウマイ弁当のおかずと中華菓子の試食も楽しめ、大人から子供まで大人気だそうです。
もともと工場見学は、域外から横浜に観光客を集めることが当初の目的だったのですが、実際には、ほとんどの見学者は地元の人たちで埋め尽くされ、横浜の人たちにとっての自慢の場所になっています。
1954年の発売から68年。「崎陽軒のシウマイ弁当」は横浜市民にとって身近な地域ブランドとして今後も受け継がれていくに違いありません。
今回は、独自の「シウマイ弁当」を看板商品に育て上げ、横浜名物として全国のファンに愛され、一方で季節の限定商品や地元とのコラボ商品の開発で、地域のファンともつながり続ける仕組みを構築。安定した成長を続ける「崎陽軒」を事例に110年以上もお客様に愛される経営手法を学んできました。
重要なポイントとしては、
① 他には真似できない独自の看板商品を育て上げること
② 昔ながらの姿を大切にしてお客様に安心感と信頼感を与えること
③ 地域に密着して、地元の人にも愛される商品を開発し続けること
④ 地元のお客様に喜んでもらえる、工場見学のような接点を増やすこと
さあ、あなたの会社でも他社にはない一番の魅力に磨きをかけ、お客様を引き寄せ、決して離さないファンづくりのマーケティングを実践して、LTVを高めていきましょう。